Blog
ブログ
VOL317 小満について
2023年5月22日
2023年5月21日(日)、二十四節季の第八番目の小満(しょうまん)です。
「暦便覧」によると、「万物盈満(えいまん)すれば草木枝葉繁る」、小満とは陽気がよくなり、草木などの生物が次第に成長して生い茂るという意味になります。ちなみににしにほんでははしり梅雨が現れる頃です。
「小満の候」とは、小満の日から、次の節季「芒種(ぼうしゅ)」の前日まで使うことができます。今年の芒種は6月6日の為、5月21日から6月5日までは「小満の候」と称することができます。
「小満の三候」
1 「初候」…蚕起食桑(かいこ起きてくわをはむ)、5月21日から5月26日頃、蚕が桑の葉をたくさん食べて成長する頃になります。人々の暮らしを支えていたため、「おかいこさま」と敬称をつけて呼ぶ地方もあります。
2 「次候」…紅花栄(べにばなさかう)、5月27日から5月31日頃、あたり一面に紅花が咲く頃になります。紅花は古代エジプト時代から染料として利用され、花弁(はなびら)の水に溶ける黄色の色素と、水に溶けない赤の色素から、紅色が作られます。
3 「末候」…麦秋至(むぎのときいたる)、6月1日から6月5日頃、麦が熟し、たっぷりと金色の穂をつける頃になります。百穀が成熟する、麦にとっての「秋」です。この時期に穂を揺らしながら吹き渡る風を「麦嵐」、又は降る雨を「麦雨」と称します。
小満の虫
●てんとう虫
よく知られている背中に斑点が7つあるナナホシテントウ、背中の黄色いキイロテントウ、病気の菌を食べてくれるテントウなど大きさ、色、様々な種類や役割を持ったテントウムシがいます。
小満の食べ物
●辣韮(らっきょう)
中国が原産で日本には19世紀までに伝来し薬用、野菜として全国に普及したと言われています。若摘みしたものはエシャロットと呼び、生食され、食欲増進効果があります。
●桜桃(さくらんぼ)
語源は桜を擬人化した「桜ん坊(さくらんぼう)」と言われています。山桜などの桜類の果実は多くのものが食べられますが、現在スーパーに並ぶのは殆どヨーロッパ種の物になります。果実に様々な味、色、形のものがあります。
●メロン
アフリカ原産で、日本には明治時代頃に入ってきたとされ、環境上栽培が難しく高価な果物の代名詞となっています。果肉は、赤肉種、青肉種、白肉種の3種類に分類されています。
小満の行事
●潮干狩り(しおひがり)
旧暦の15日頃は潮の干満の差が大きく「大潮」と呼ばれ、この時期は多くのかいが見つかりやすいとされています。熱中症に注意し、熊手とバケツを持って皆んなで楽しく取りに行きましょう。

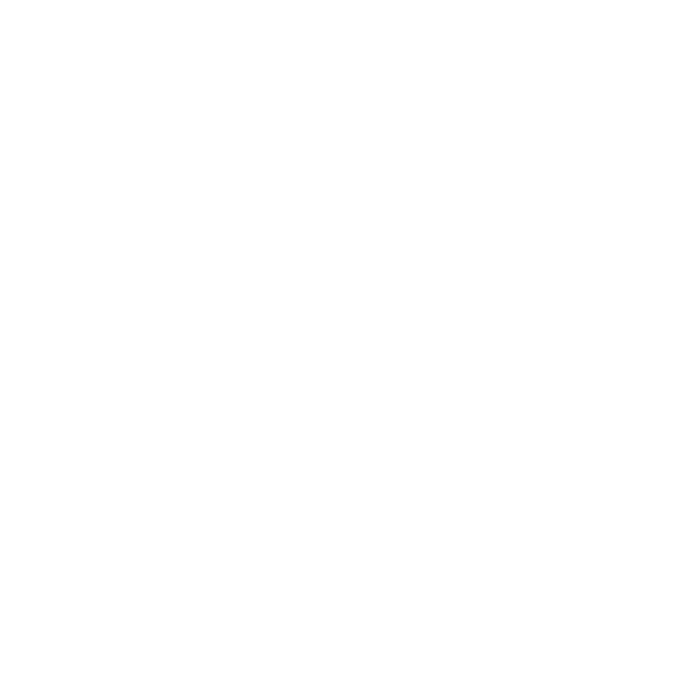 会社案内
会社案内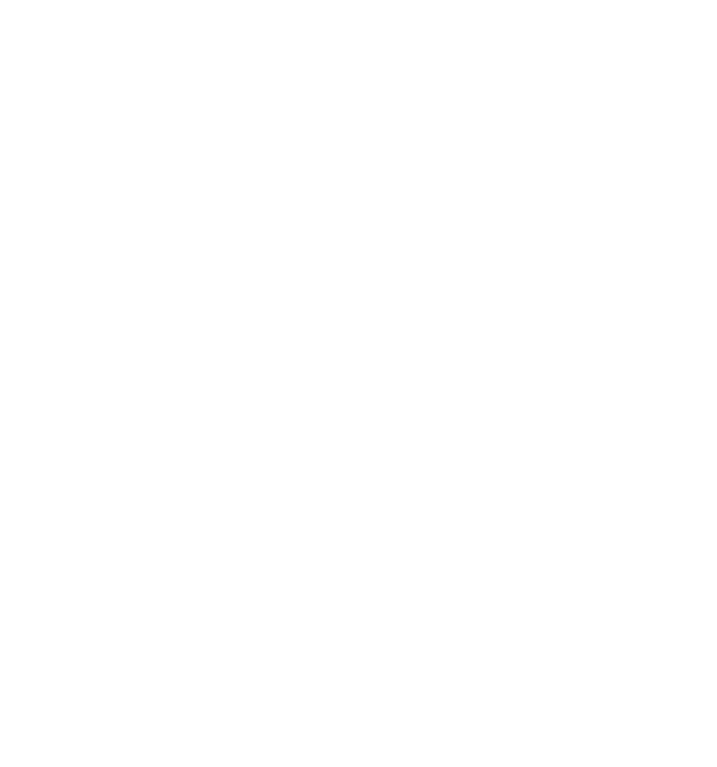 商品一覧
商品一覧