
7月22日(月)、二十四節季の第十二番の大暑(たいしょ)です。「暦便覧」によると、「暑気いたりつまりたるゆえんなれば也」、大暑はとは最も暑い頃という意味であるが、実際最も暑くなるのはもう少し後、夏の土用の時期になります。体力を保つために鰻を食べる「土用の丑」や、各地でお祭り、花火大会もこの時期にたくさん開かれ、夏の風物詩が目白押しです。また、学校は夏休みに入り、空には雲の峰が高々と聳えるようにもなります。
「大暑の候」とは、大暑の日から、次の節季「立秋(りっしゅう)」の前日まで使うことができます。今年の立秋は8月7日(水)の為、7月23日から8月6日までは「大暑の候」と称することができます。
「大暑の三候」
1 「初候」…桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)、7月22日から7月26日頃、盛夏を迎える頃には、卵形の実を結びます。桐は伝統的に神聖な木とされ、豊臣秀吉などの天下人が好んだ花であり、現在も日本国政府の紋章として使用されています。
2 「次候」…土潤溽暑(つちうるおうむしあつし)、7月27日から8月1日頃、熱気が纏わり付く(まとわりつく)蒸し暑い頃になります。私たちは、この暑さを打ち水などで凌ぐ(しのぐ)ことしかできませんが、木や草花は緑を益々濃くして夏を歓楽(かんらく)しているようです。
3 「末候」…大雨時行(たいうときどきにふる)、8月2日から8月6日頃、夕立や台風などの夏の雨が激しく降る頃になります。綺麗な青空に湧き上がる入道雲は、夕立を教えてくれます。雲の頭が坊主頭に見えることから、入道雲と呼ばれています。
大暑の食べ物
●ゴーヤー
沖縄県の特産物であるゴーヤーは、独特の苦味があり、水にさらしたり塩揉みをしたりすることで苦味が軽減されます。
●ズッキーニ
ズッキーニにはビタミンCが豊富に含まれ、コラーゲンの生成を促す効果が期待できます。また、カリウムは体内の余分なナトリウムを排出に、むくみ解消効果がきたいできます。さらに、葉酸は細胞の生まれ変わりを促進する効果があると言われています。
大暑の花
●白粉花(おしろいばな)
黒い種の中にある白い粉を少女たちがおしろい代わりにして遊んでいたことから、この名前が付けられたというのです。花は夕方に開き始め、翌朝に萎んでしまうことから、夕化粧とも呼ばれています。
大暑の行事
●ねぶた祭/ぬぷた祭
「ねぶた(ねぷた)」という言葉は「眠り」が元で、睡魔をはらう「眠り流し」という意味合いからきているという説があります。また、7月7日の夜に灯籠と一緒に穢れ(けがれ)を川や海に流して無病息災を祈る行事だった「七夕祭り」があり、その灯籠(とうろう)が「ねぶた」と呼ばれたことから「なぶた流し」隣、今の青森ねぶた祭のねぶたの海上運行がその名残となっている説もあります。現在は、たくましい武者の絵が描かれた灯籠がまちを練ります。
大暑の虫
●カブトムシ
カブトムシはいつの時代も夏の昆虫の王様で、にょきっと頭に生えた立派な角、相手の虫をひっくり返してしまう様子は迫力があります。
大暑の魚
●金魚(きんぎょ)
夏祭りの定番であり、子供から大人まで人気のある「金魚すくい」。金魚とは中国語金余と同じ発音で、お金が余ることから金運上昇の意味があり、縁起物とされています。


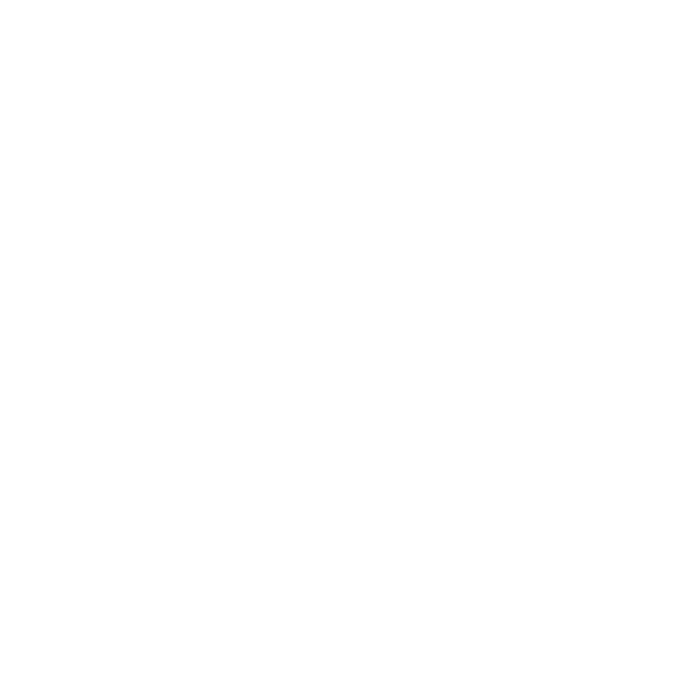 会社案内
会社案内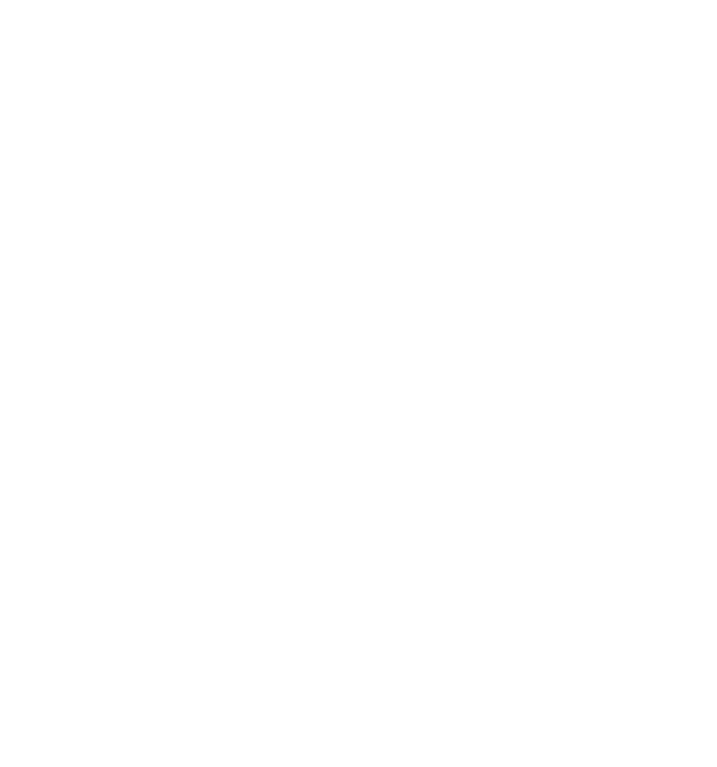 商品一覧
商品一覧


















